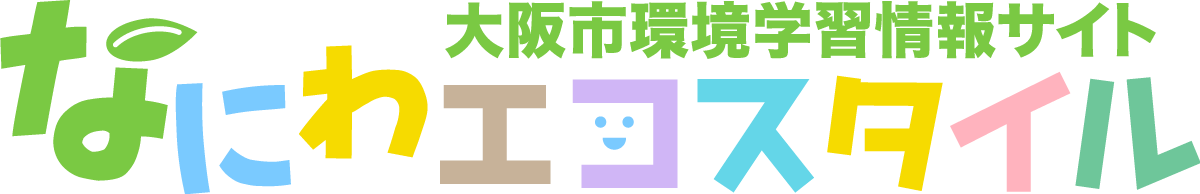おおさか環境ネットワーク会議レポート 令和6年度 第4回
日時:2025年1月29日 17時から19時30分まで
場所:大阪市環境局第1会議室
参加団体:12人(順不同)
リアルにブルーアースおおさか(対面)
地球環境市民会議(CASA)(対面)
自然エネルギー市民の会(対面)
木育フォーラム(対面)
環境事業協会(オンライン)
大阪自然環境保全協会(オンライン)
なにわエコ会議(対面)
大阪府シェアリングネイチャー協会(オンライン)
環境局:2人
事務局:4人(対面及びオンライン)
1 勉強会
(1)温暖化問題~現状と課題~
発表者: NPO法人地球館環境市民会議 宮崎氏
・地球温暖化の現状
世界の平均気温は産業革命前から1.55℃上昇し、2024年には過去最高を更新。
日本では過去100年で1.4℃上昇、大阪ではヒートアイランド現象により2℃上昇。
異常気象による被害が多発し、熱中症による死亡者数も増加。
グテーレス国連事務総長は地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来たと警告。
・温暖化の原因と影響
主な原因は二酸化炭素排出であり、化石燃料の使用が最大の要因。
気温上昇により、グリーンランドや南極の氷床融解、サンゴ礁の減少、永久凍土の融解などが進行。
農業では作物の不作や品質低下、漁業では魚種の減少や適地変化などが起こり、第一次産業従事者の生活を脅かす。
熱中症などの健康被害や、住居・食料・水などの人権問題も深刻化。
・温暖化対策
緩和策として、再生可能エネルギーへの転換や省エネの推進が重要。
適応策として、被害を最小限に抑えるための対策が必要。
国際社会は平均気温上昇を1.5℃に抑える目標を掲げているが、現状の対策では不十分。
個人レベルでは、省エネ家電への買い替えや再生可能エネルギーの利用、公共交通機関の利用などが有効。
社会全体での取り組みとして、建物の断熱化や公共施設への太陽光発電設置などが重要。
・まとめ
地球温暖化は人類にとって深刻な脅威であり、早急な対策が必要である。
国際社会全体での取り組みに加え、私たち一人ひとりの意識改革と行動が求められている。
(2)再生可能エネルギーについて
発表者: 自然エネルギー市民の会 島田氏
・自然エネルギー市民の会
2004年設立。
地球温暖化防止のため、市民参加型の発電所建設・運営を行う。
母体は市民風車を作る会。
・日本の電源構成と課題
LNG、石炭、原子力に大きく依存。
原子力発電は核廃棄物問題、化石燃料は資源枯渇、地球温暖化問題を抱える。
・小規模分散型発電
再エネ利用による小規模分散型発電が注目されている。
防災面でも有効性がある(千葉県六崎町の事例)。
・再エネの現状
世界的に導入が進んでいる。
日本でも導入ポテンシャルは高い。
太陽光、風力、小水力などが主な種類。
・再エネ導入の課題
地域特性に合わせた導入方法の検討が必要。
地域住民との合意形成が重要。
・市民レベルの取り組み
電力会社の選択(パワーシフトキャンペーン)。
太陽光発電の共同購入(大阪スマートエネルギーセンター)。
市民共同発電所の設置。
・まとめ
地球温暖化対策として、再エネ導入は不可欠である。
市民レベルでの取り組みも重要であり、電力会社の見直しや、太陽光発電の共同購入などを通じて、再エネ普及に貢献できる。
(3)NPO法人リアルにブルーアースおおさか活動報告
市民共同発電所の設置と活用について、動画で説明があった。
(4)日本のエネルギー政策~第7次エネルギー基本計画~
発表者: NPO法人地球館環境市民会議 宮崎氏
・エネルギー基本計画の問題点
2030年までの具体的な取り組みが示されていない。
原発推進、化石燃料継続の方針が明確。
大企業優先の政策であり、消費者の視点が欠けている。
気候変動対策が経済発展の手段として位置づけられている。
計画策定メンバーが原発推進派や経済界代表に偏っている。
・CO2削減目標の乖離
日本の2030年、2035年の削減目標は国際目標より大幅に低い。
2040年の目標も達成可能かどうか疑問が残る。
・再生可能エネルギーの遅れ
日本の再生可能エネルギー導入は主要国に比べて大幅に遅れている。
ポテンシャルはあるものの、政策的な支援が不足している。
・原発推進の問題点
コストが高く、安全性に問題がある。
事故時のリスクが大きい。
核廃棄物問題が未解決。
・水素利用の問題点
大手電力会社や産業界の利害を優先した政策。
再生可能エネルギーを水素に変換して利用することの非効率性。
・電気自動車の問題点
ハイブリッド車も「電動車」に含めることで、CO2排出量削減効果を曖昧にしている。
電気自動車への移行を促進する政策が不足している。
・まとめ
日本のエネルギー基本計画は、脱炭素化に向けた具体的な戦略に欠け、多くの問題を抱えている。
このままでは2050年の脱炭素目標達成は困難であり、抜本的な政策転換が必要である。
(5)質疑応答
・風力発電
日本でも導入が進められているが、まだ伸びは少ない。
発電効率が良いが、漁業との兼ね合いや国立公園内での開発など課題もある。
・地熱発電
ポテンシャルは高いが、開発許可や温泉事業者との合意形成が難しい。
コストも高く、リスクが大きい。
・太陽光発電
コストは低下しているが、再エネ賦課金の問題や廃棄問題がある。
2030年の発電コスト予測は、ウクライナ情勢などの影響で不確実。
・原発
運転中の原発は電気料金が安いが、新設には莫大なコストがかかる。
安全性や核廃棄物問題も未解決。
・大規模集中型発電 vs 小規模分散型発電:
大規模集中型発電は送電線の問題、小規模分散型発電は安定供給の問題がある。
それぞれのメリット・デメリットを考慮して選択する必要がある。
・再生可能エネルギーの廃棄問題
太陽光パネルなどの廃棄問題は深刻化しており、対策が必要。
国は廃棄費用積み立て制度を導入しているが、実効性に課題も残る。
・結論
質疑応答を通じて、エネルギー問題の複雑さと多様な側面が明らかになった。
それぞれのエネルギー源にはメリット・デメリットがあり、課題も山積している。
今後のエネルギー政策は、これらの要素を総合的に考慮し、持続可能な社会の実現を目指して策定される必要がある。
2 近況報告
無し
3 今後の取組みについて
・夏休みのイベント
参加者が多く、好評だったため、次年度も継続することで合意。
・勉強会
継続については賛成意見が多かった。
形式や内容については、過去の事例を参考にしながら検討する必要がある。
参加者の意見交換や問題提起の場としての役割も期待された。
・地域との連携
地域住民への啓発活動や地域イベントへの参加など、地域との連携が進められるか?
自治会へのアプローチも有効か?
・学校との連携
教育委員会やPTAへのアプローチ、学校への出前授業など、学校との連携を強化する必要がある。
学校教育における環境教育の重要性も指摘された。
・大阪市の環境政策
環境教育に関する副読本の配布やタブレット授業などが行われている。
脱炭素戦略については、具体的な施策が検討されている。
・結論
次年度は、夏休みのイベントと勉強会を継続しつつ、地域や学校との連携を強化することで、より効果的な活動を目指す。
大阪市の環境政策も活用しながら、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいく。
4 PRタイム
無し